小児の肺炎球菌感染症 予防接種
小児の肺炎球菌感染症の予防接種について
対象者
生後2カ月から60カ月(5歳となる日の前日まで)に至るまで
接種スケジュール
- 接種開始が生後2カ月~生後6カ月の場合…4回接種(標準的な受け方)

- 初回免疫2回目・3回目の接種は、2歳になる前までに行う。2歳を超えた場合は 行わない。(追加免疫は可能)
- ただし、初回免疫2回目の接種は1歳になる前までに行う。1歳を超えた場合は初回免疫3回目は行わない。(追加免疫は可能)
- 接種開始が生後7カ月~生後11カ月の場合…3回接種

- 初回免疫2回目の接種は、2歳になる前までに行う。2歳を超えた場合は 行わない。(追加免疫は可能)
- 接種開始が1歳の場合(2回接種):60日以上の間隔をあけて2回
- 接種開始が2~4歳(1回接種)
接種にあたっての注意
- 接種開始時や接種日当日の月齢・年齢により、接種回数と間隔が異なりますので、事前によく確認してから接種を受けましょう。
- 令和6年10月1日から、20価ワクチンと15価ワクチンの2種類となり、原則、20価ワクチンを使用します。15価ワクチンで接種を開始した場合は、15価ワクチンで接種を完了します。途中でワクチンの変更はできません。(15価ワクチンと20価ワクチンの交互接種については、安全性、有効性のデータがないため)
肺炎球菌による感染症について
肺炎球菌は、主にこどもの鼻やのどの粘膜に感染・定着し、そのまま何の症状も引き起こさず発症しないこともありますが、体調を崩したり、ほかの感染症にかかったりすることで発症のリスクが高まります。
乳幼児や高齢者では肺炎や中耳炎、副鼻腔炎などを引き起こすほか、何かのきっかけで脳や脊髄を包む髄膜、肺や血液などに入り込むと命にかかわる重い感染症(細胞性髄膜炎、喉頭蓋炎菌血症、敗血症、肺炎など)を発症する場合もあります。
肺炎球菌は、喉や鼻の奥に住み着いている身近な菌のため、誰でも重い感染症にかかる可能性があります。
ワクチン接種により肺炎球菌(ワクチンに含まれる種類のもの)が血液や髄液から検出されるような重篤な肺炎球菌感染症を95%以上減らすことができると報告されています。
細菌性髄膜炎について
細菌が髄膜(ずいまく)という脳や脊髄を包んでいる膜に感染して炎症を起こす病気です。
特に乳幼児や高齢者では急速に進行し、命にかかわる危険性や後遺症が残るリスクがあります。発症すると、発熱、けいれん、嘔吐、意識障害、首の硬直などの小ショウガみられ、乳幼児ではぐったりし元気がない、泣き止まないなどのサインが現れることもあります。
進行が速く、症状が悪化し、高熱やけいれん、意識障害が出て初めて判断がつくことが多く、早期の判断が大変難しい病気です。細菌性髄膜炎の原因となる細菌(起因菌)はいくつかありますが、多くはHibと肺炎球菌が原因と言われています。
肺炎球菌による髄膜炎はヒブによる髄膜炎より頻度は低いものの重篤とされています。
細菌性髄膜炎にかかっても、早期に判断がつき治療薬の効果があれば、無事に回復する
ことができますが、薬の効果がない耐性菌が増えているために、治療が難しく、死亡(2%)や生存した子どもの10%に難聴、精神発達遅滞、四肢麻痺、てんかんなどの重い後遺症を残すといわれています。
小児の肺炎球菌ワクチンの副反応
注射部位の赤み、はれ、しこり、痛みや発熱、不機嫌、食欲不振、蕁麻疹などで、これらは通常数日以内に自然に治ります。
まれに重い副反応として、ショック、アナフィラキシーけいれん(熱性けいれん含む)、血小板減少性紫斑病などが報告されています。
小児の肺炎球菌リーフレット (PDFファイル: 2.1MB)
詳細は、厚労省のページをご参照ください。
このページに関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050

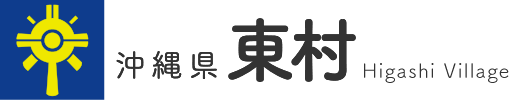

更新日:2025年09月26日