5種混合ワクチンのご案内
5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ)について
ジフテリア・百日せき・ポリオ・ヒブの1期定期予防接種の種類は、
- 5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ)
- 4種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)とヒブワクチン、DT等
があります。なお、定期予防接種を始める場合は、原則、5種混合を使用します。
対象者
生後2カ月から7歳6カ月となる日の前日までの間にある児
接種回数と間隔
第1期4回(初回接種:3回、追加接種:1回)
- 第1期初回の標準的な間隔は『20日~56日までの間隔』です。
- 第1期初回の標準的な接種期間は生後2カ月~7か月の間です。
- 追加接種は、標準的には初回接種終了後6~18カ月の間です
標準的な接種期間・間隔は、病気にかかりやすい年齢や免疫のつけやすい間隔を考慮して定めたものです。標準的な接種期間・間隔を過ぎても接種は受けられます。
ジフテリア(D)について
ジフテリア菌の飛沫感染や接触感染で起こる病気です。主にのどや鼻に感染し、高熱、のどの痛み、嚥下痛(飲み込み時の痛み)などで始まり、犬が吠えるような咳がみられます。
気道にも膜状の膿が現れるため、呼吸困難になり、重篤な合併症を引き起こし窒息死することもある感染症です。またこの菌が出す毒素は、心臓の筋肉や神経を侵すため、発病後に心筋炎や神経麻痺などの心筋障害を引き起こすことがあり、これらの合併症が原因で突然死亡することもあります。
近年、海外からの感染者が増えており、ワクチン接種率の低い外国からジフテリア菌が持ち込まれるリスクも高まっています。
百日せき(P)について
百日咳は、百日咳菌の飛沫感染によって起こる病気です。普通の風邪のような症状で始まりますが、次第に咳がひどくなり、顔を真っ赤にして連続的に激しく咳き込むようになります。咳の後、急に息を吸い込むので笛を吹くような音が出ます。発作的な咳が繰り返し、しばしば1分以上続くことがあり、この咳が百日以上続くことから名前が付けられています。
特に乳幼児や高齢者は重症化しやすく、激しい咳で息を吸う間がないために呼吸ができず、唇が青くなったり(チアノーゼ)、痙攣が起きたり、肺炎や脳症を引き起こし死亡することもあります。
近年、成人における百日咳の発症が増えており、成人が乳幼児への感染源となる危険性があります。
破傷風(T)について
破傷風菌によって引き起こされる感染症です。この菌は世界中の土壌や動物の排泄物に存在し、常に感染の危険性があります。深い傷だけでなく、土いじり等でできる小さな傷でも起こります。
傷口から侵入した破傷風菌が出す毒素により中枢神経を侵し、痙攣を起こす病気です。破傷風の主な症状は筋肉の強いこわばりと痙攣です。口が開けにくくなり、歯がかみ合わさった状態(開口障害)、顔面筋の緊張・硬直によりひきつった顔になるなどの局所の痙攣症状から始まります。続いて全身性の痙攣が起こり、重症化すると呼吸筋の麻痺により窒息死することもあります。
破傷風は自然感染によって免疫を獲得できないため、予防接種以外に免疫をつける方法はありません。予防接種を定期的に受けることで感染を防ぐことができ、破傷風から身を守る最も確実な方法です。
ポリオ(IPV)について
ポリオ(急性灰白髄炎)は、ポリオウイルスによって引き起こされる感染症で【小児まひ】
と呼ばれ、主に手足に麻痺を起こす病気です。
ウイルスは口から体内に入り、腸で増殖した後、神経系に感染し、筋肉の麻痺を引き起こします。重症の場合は呼吸筋が麻痺し、呼吸困難で死亡することもあります。ポリオは主に糞便や飛沫を通じて感染しますが、予防接種により完全に防ぐことが可能です。
日本では1950年代に流行がありましたが、予防接種の普及により国内での発症はほぼなくなりました。しかし、海外では依然として発症例があり、国際的な感染拡大のリスクが存在します。予防接種を受けることで、ポリオの感染拡大を防ぐことができます。
ヒブ(Hib)について
ヒブ(インフルエンザ菌)は、ヒブ菌の飛沫感染や接触感染によって起こる病気で、特に乳幼児や免疫力が低下している人々に重篤な影響を与えることがあります。何かのきっかけでこの常在菌が脳や脊髄を包む髄膜、肺や血液などに入り込むと、命に係わる重い感染症(細菌性髄膜炎、敗血症など)の原因となる場合があります。
インフルエンザウイルスと名前が似ていますが全く別物です。ヒブは毎年流行するわけではなく、特に免疫が未発達な乳幼児や高齢者が感染しやすい病気で、ヒブによる細菌性髄膜炎の患者は5歳未満で多くみられます。
5種混合ワクチンの副反応
接種部位の赤み、腫れ、しこりが見られることがあります。接種部位以外の副反応としては発熱、発疹、咳、鼻水、のどの赤み、下痢、食欲減退、嘔吐、気分変化、不機嫌などが報告されています。
ほとんどの場合、副反応は軽度で一時的なもので、極めて稀ですが、アナフィラキシー(呼吸困難、じんましん、血管浮腫等)、血小板減少性紫斑病、脳症、痙攣などの重い副反応が起こることもあります。
このページに関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050

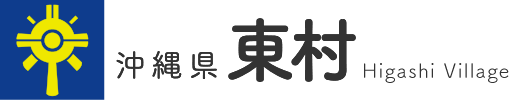

更新日:2025年09月18日