おたふくかぜワクチンの予防接種費用の一部を助成します
ご確認ください
おたふくかぜは、ムンプスウイルスの感染によって起こる感染症です。
東村では村民の経済的負担を軽減するとともに、おたふくかぜの発症及び重症化の予防とその蔓延を防ぐことを目的とし、接種を受ける方の費用の一部を助成します。
おたふくかぜ予防接種は、現在、予防接種法に基づかない任意の予防接種となっており接種の義務はありません。
接種を受けるかどうかは、効果や副反応等を考慮したうえで、ご判断ください。
ワクチン接種についてご心配なことがありましたら、接種を行う前に必ず主治医等にご相談ください。
接種時期について
おたふくかぜは、2~7歳での発病が多いため、1歳になったらできるだけ早期に接種することが望まれています。
日本小児科学会では、予防効果を確実にするために1歳と小学校就学前1年間(5歳以上7歳未満)の2回接種が推奨されております。(時期が同じMRワクチンと同時接種をお奨めします。)
対象者
接種日当日東村に住所のある1歳の誕生日から小学校就学前の3月31日にある方
(ただしこれまで2回以上接種した方、罹患した方は対象外です)
助成の範囲
- 自己負担分1,000円を超えた額
例:予防接種費用3,500円を支払った場合
3,500円-1,000円=2,500円
2,500円が助成されます。 - 1人につき1回まで
予防効果を確実にするため2回接種が推奨されています。ただし、2回目の接種費用は、全額自己負担となります。
接種までの流れ
- ワクチンの効果、副反応、助成の対象条件等を確認する。
- かかりつけ医療機関へ事前にご予約の電話をする。
- 予防接種を受ける。
接種方法
接種量0.5mlを皮下に1回接種します。
持ち物
- 母子健康手帳(接種の記録、他の予防接種との間隔等を確認します。)
- 健康保険証又は東村子ども医療費助成金受給資格者証等(東村民であること、接種対象者であることを確認します。)
予診票は医療機関のものをお使いください。役場からの予診票発行・発送はございません。
助成方法
償還払いのみ
医療機関で一旦予防接種料金を全額お支払いし、役場福祉保健課窓口で助成の手続きが必要です。後日申請を行ってください。
助成申請期限:予防接種を受けた日の翌日から1年以内
持ち物
- 医療機関から受け取った領収証(おたふくかぜの予防接種を行ったことが明記されたもの)
- 保護者名義の振込口座番号が分かるもの(預金通帳等)
- 認印(シャチハタ不可)
おたふくかぜとは
おたふくかぜは流行性耳下腺炎あるいはムンプスとも呼ばれ、ムンプスウイルス感染によって起こる全身性感染症です。
感染方法は、咳やくしゃみなどの飛沫感染や接触感染で、感染してから2~3週間の潜伏期間の後に耳下腺や顎下腺などの唾液腺の腫れや発熱を発症します。
合併症として膵炎、ムンプス難聴と呼ばれる高度感音難聴や髄膜炎等があり、思春期以降に感染すると、精巣炎や卵巣炎を起こすこともあります。
髄膜炎は合併症として珍しくなく、おたふくかぜの経過中の発熱・頭痛・嘔吐は髄膜炎を疑う症状として要注意です。
また、ムンプス難聴は重大な合併症で、発症すると聴力の回復は難しく、その後の日常生活にも影響をきたします。さらに、学校伝染病であるため耳下腺の腫れがひくまでは出席停止となります。
副反応について
接種後に発熱や耳下腺脹等がみられることがありますが、通常、症状は数日で軽快します。
無菌性髄膜炎は、0.04~0.06%の頻度で発生するとの報告がありますが、自然感染による発生頻度(1~10%)と比較すると、予防接種をしたほうが髄膜炎に対するリスクは低いと考えられています。
外部サイトリンク
【沖縄県ホームページ 】予防接種による健康被害救済制度について
任意の予防接種による健康被害救済制度について掲載されています。
『ムンプス』『流行性耳下腺炎』で検索すると色々な記事があります。
このページに関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050

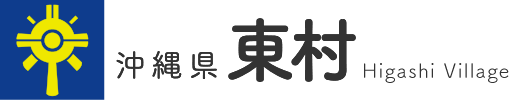

更新日:2025年07月31日