赤土流出について学ぼう!
赤土流出とは?
沖縄では地形や土壌の特性等により、まとまった雨が降ると、開発現場や農地・米軍基地などから、細かい粒子の土「赤土」が川や海に流れでることを赤土流出といいます。流出した赤土は雨水とともに河川に流れ込み、海へ流下し拡散します。拡散した赤土は海を濁らせ、時間が経つと海底に沈み堆積することで一時的に表面はきれいになりますが、海の状況により巻き上げられ再び海を濁らせます。
流出の割合:米軍基地3% 開発事業10% 農地84% その他3%

宮城区 古島川

平良区 推川
赤土等の流出による影響
赤土等が堆積することで、河川や海の水中生物の生態系に影響し、魚介類の産卵場所の喪失、サンゴ礁の基盤となっているサンゴの減少などにつながります。またそれに伴い漁業(潜り漁やモズクなどの養殖業等)への影響、観光業(マリンレジャーや自然体験等)へも悪影響を及ぼします。
沖縄県赤土流出防止対策プロジェクトにおいても紹介されていますのぜひご覧ください。
東村における降雨後の海の状況写真

宮城区(古島川)から広がる

赤土平良(推川)から広がる赤土

流出した赤土が沖に広がる様子

赤土によるモズク被害

サンゴがなく荒廃した状況

赤土による海の濁り
写真提供:沖縄県水産海洋技術センター
このページに関するお問い合わせ先

建設環境課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2205
メールアドレス:okh47014@vill.okinawa-higashi.lg.jp

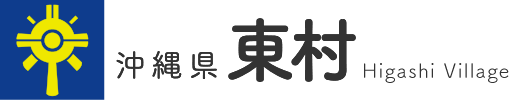

更新日:2023年10月13日